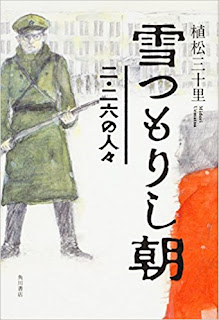|
| 本阿弥書店より出版 |
作者の毬矢まりえさんは、若くして海外で学ばれた国際派で、西洋文学の研究家であると同時に俳人として、俳句の世界遺産登録申請運動にも携わる活躍ぶり。この本は、究極の芸術表現ともいえる俳句を、西洋芸術と比較して論じたものである。
正岡子規が、友人の画家中村不折を通じて西洋絵画の「写生」の概念を知り、それを句作に適用して近代俳句の基礎を作った一方で、フランスの批評家ロラン・バルトや詩人のポール=ルイ・クシューが、芭蕉や蕪村に影響されていたーー。こうした国際間の相互作用が、たくさんの例句を引いて、詳しく書かれている。
私たちが何気なくやっている俳句だが、たしかに宗祇がいて、芭蕉がいて、蕪村がいて、子規がいて、虚子がいて、そうやって時代とともに俳句という表現形式に息を吹き込んできてくれたからこそ、いまここに歳時記もあり、さまざまな結社や俳誌があって、俳句という文化も存在するのだろう。その過程には、子規のように新たな表現方法を探して西洋の概念を取り入れる人もいたし、同様に西洋にもまた日本の俳句から、表現の神髄を学ぼうとした人たちがいる。
ジャポニズムがあれだけ印象派に影響を与えたように、あるいは、フランク・ロイド・ライトやアントニン・レーモンドが日本建築からインスパイアされたように、俳句もまた多くの西洋の表現者にとっては、魅力のあるものらしい。「俳句は羨望を起こさせる。その簡潔さが完璧さの保証となり、その単純さが深遠さの確認となる」とはロラン・バルトの言葉。
作者は、本の冒頭でマルセル・プルーストの散文を挙げ、彼の試みた、丹念な写生や描写の積み重ねによって到達しうる自然の深遠な境地を、俳句という形式がたったの17文字で成し遂げる可能性について論じている。そして虚子の晩年の句――明易や花鳥諷詠南無阿弥陀――を引いて、感動が深遠なものへと、物から心へ、より高きものへ向かうのだと説く。
さらに、彼女は俳句をなんとダークマター(おお、私の大好きな暗黒物質!)になぞらえる。
ダークマターは宇宙に確かに存在し、この宇宙に大きな影響を与え続けている物質である。俳句もまた文学という宇宙空間に確かに存在し影響を与えるものとはいえないだろうか。俳句の一句一句は小さいものかもしれない。太陽のように巨大な発行体として君臨しているのではないだろう。けれど俳句は多様な国々に革新的な影響を与えてきたのである。多くの文学者、芸術家にインスピレーションを与えているのだ。
繊細かつ簡潔、イメージ力に溢れ、大胆でありつつ洗練された俳句。伝統と革新が両立し、小景も遠景をも包含してしまう俳句。クーシューはそのような俳句を「一瞬の驚き」とも評している。一瞬一瞬を切り取り表現してしまう日本人の感性に、ヨーロッパ人は感嘆したのである。
「俳句とはポエジーのダークマターではないか」、と作者は言うのだが、まあこの飛躍が俳句的ともいえるのかもしれないが、ずいぶんと大仰な(笑)。しかし、俳句が一瞬一瞬を切り取って表現する、日本人独自の感性だと言われれば、たしかにそれは面白い。
作者は俳句をカンディンスキーのコンポジションにもなぞらえる。コンポジションとは、画家が視覚的に獲得したものをいったん内面的に沈潜させ、検討し練り上げてから組み立てる(コンポーズ)するもので、自然や事物をありのままにリアリスティックに表現するのとは違うという。「内面的視力」を持つことで、吸い殻のような小さき命のないものも、「魂」を打ち明け、「心の秘奥」を体得できる・・・いわゆる「心の目」でみるということ。一方で、心を空しくして見なければ、自然の本来の姿は見えてこないともいえるのだが。
このほか季語についてもさまざまに考察されている。何気なく使っている季語だが、これもまた、日本人独特の感性が長年をかけて編んできた文化遺産だと言われれば、すんなり納得できる。
ニュージーランドの知人宅にいたときのことである。外では蝉が鳴いていた。「うるさいわね」と顔をしかめる彼女に私は言った。「日本では蝉の声を蝉の雨(蝉時雨)といって、夏の風物詩として愛でるのよ、そればかりじゃなくて、蝉の抜け殻や落ちて死ぬ蝉までも。蝉の抜け殻って英語でなんて言うの?」「a cicada’s case?」「うわ、そのまま。日本では蝉の抜け殻が、千年以上も前に書かれた長編小説の主人公の恋人の名前になるくらい風情のあるものなのよ!」
英語の辞書で引くと、空蝉は「cicada’s shell」となっているが、shell (殻)だろうがcase(入れ物)だろうが、ニュージーランド人(あるいは英語のネイティブ)にとってはどう呼んでもかまわないくらい、取るに足りない、風情など全く感じ得ない、たんなる抜け殻なのだ。といっても、日本人だって俳句をやらない人にとっては、どうでもいいものなのかもしれない。昔から季語として愛されているがゆえに、風情を感じる・・・という逆説も成り立つ。
桜だって、朝咲こうと夜咲こうと、俳句をやらない人には同じだが、歳時記に、朝桜、夕桜、夜桜とあれば、それぞれの違いを感じようとするし、花の雨、花曇り、などといわれれば、せっかくの桜の時期なのに残念だなどと思わずに、しっとりした情緒を味わえたりもする。そう考えると、季語は日本人ならではの感性の結晶であり、日本人にうまれたのなら俳句をやらなければ損だという気もしてくる。
一方で、作者は、こうした季語の持つ一定のイメージないしは虚構性が、俳人の足かせにもなり得ると警告する。例えば、「蝉時雨」という季語によりかかり、実際の蝉の声を自分の耳でしっかりと聴かなければ、季語が死んでしまうという。
俳句をとても英語にはできないと思っているので、俳句の国際化というものがピンとこなかった私だが、この独特の形式が、他国の人に影響を与えることは、この本で納得がいった。しかし、風土というものを考えると、やはり日本のこの四季があっての俳句であり季語であると思う。それは、一般に言われているように、日本が自然というものに親和性があるからというのは、あくまでも西洋との比較であり、インドや台湾に暮らしたことのある私からしてみれば、熱帯性の国の方がもっと生活と自然が密な気がする。特にインドでは、地べたに座って裸足で歩き、箸やフォークを使わずに手で食べたりもしたし、自分自身がもっと自然と一体化している感覚になれる。スラム街では、周りにある素材――場所によっては、石、土、粘土、段ボール、ビニールシートなど――を使い、隣家の壁を自分の家の壁として、まるで細胞が分裂していくような形で増殖していく暮らしぶりも目の当たりにした。という意味からいって、日本人は自然と一体というより、自然を身近に感じつつも間接的に捉え、信仰の対象として、また心象の表出手段として扱ってきたと思われる。そうした客観性がなければ、ただ落ちただけの椿、枯れた蓮などを愛でる文化は生まれまい。
それにしても、落椿や枯蓮・破蓮など、日本人は自然を愛でるといいつつも、意外とネガティブというか、生命賛歌とは言えない季語が多いことに驚く。蛇の衣とか、凍滝とか、枯野とか、生命感の乏しいものに思いをはせるのも、カンディンスキーの言う「心眼」のなせる業か。
英語には形容詞が多く、たとえば日本語の「おいしい」を表現しようと思ったら、いくつもの言い方が思いつく。日本人がよく使うdeliciousだとかtastyだけでなく、yummy, wonderful, super, fabulous, beautiful, great, amazing・・・とキリがないくらいに。逆にネガティブな形容詞も多い。つまり、ポジティブとネガティブを表現するには、とても豊富な言い回しがあるのだが、その間の微妙なニュアンスの言葉が少ないような気がする。「風情がある」「味がある」などという言葉は、とても一言では英語で言えない。
蚯蚓鳴く、亀鳴く、紙魚走る、蟭螟(蚊のまつ毛に棲むと言われる架空の虫)などの滑稽味のある表現や虚構の季語も面白い。そして、この高度に洗練された独特の感覚から生まれた季語を使って、作者ならではの見立てで、心眼を持って、卑近な人事はもちろん、蟻の穴を覗いて宇宙の果てまで見てしまえるような闊達さというか、スケールの大きさがある、それが俳句の面白さだろう。
ところで歳時記には現代の私たちにはもはやなじみの薄い季語も多いが、日本人である以上、祖先から受け継いだ記憶から、見た事がなくても、あるいは使ったことがなくても共感できるとして、作者は、蚊帳、火鉢、竈猫などの句を挙げている。一方で限界もあり、若い世代の俳人に季重なりの句があるのはその表れだともいう。ほのぼのと餅は黴つつ春を待つ(大谷弘至)・・・たしかに餅、黴、春を待つ、と三つの季語がある。
この本では、このほか、山口誓子、沢木欣一、小池文子という三人の俳人を取り上げ、俳句の中に受け継がれる芭蕉以来の漂白の精神についても論じている。そこには日本人特有の無常観があり、季語の中にも移ろいを表すもの―――初霜、冴え返る、春動くなど、季節の微妙な動きを示すものが多いと指摘する。
私は、20年ほどやってきた俳句の壁にぶつかってもがいているところなので、参考までにこの本を読んでみたのだが、いろいろな示唆に富んでいて、たしかに俳句は日本の宝であること、しかも俳句をやるやらないにかかわらず私たちの祖先が築き上げてきた、生活に根差した美意識、あるいは滑稽・おかしみ・達観(つまり俳諧味)や無常観のなかから生まれてきたという事実に気が付いた次第である。
日本人としてこんな魅力的な俳句を、やっぱりやめられそうにない。よって、自分の心眼をどう磨くか、それが目下の課題であろう。