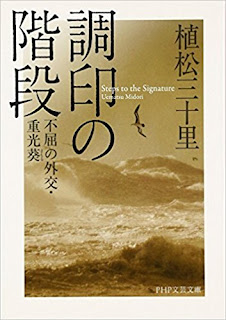|
| 1939年のライトの講演記録 |
フランク・ロイド・ライトの本や論文はかなり読み込んできたが、このたび、アマゾンからまた待望の一冊の本が届いた。それは1939年に 王立英国建築家協会で行われた4日間にわたるライトのスピーチをまとめた『An Organic Architecture』というタイトの本で、このたびライト生誕150周年を記念して復刻版が発売されたのである。邦訳は持っているが、とても大好きな本なので、原文が読みたかったのだ。
ところが、この本には再版特別企画として、アンドリュー・セイント教授という「高名な建築歴史家」による序文が載っていた。そして、それには本当に驚かされた。いったいこの本の出版の趣旨は何なのだろう!?
セイント教授は、ライトの講演が、集まった多くの聴衆にとって期待外れで、内容がなく、現実味もなく、矛盾だらけだと指摘する。そして当時その講演に参加してがっかりしたというとある建築家のコメントを長々引用している。以下はその引用文の最後。
Mr. Wright, who has a distinct gift of wisecracks, set himself to score off them and to raise a laugh at their expense, which he easily did.
辛辣なジョークを飛ばす才能を持つライト氏は、観衆をバカにして笑いを取ることを簡単にやってのけた。
そして セイント氏は序文をこう締めくくる・・・
So, there was no mutual meeting of minds at the RIBA (the Royal Institute of British Architects). For the rest of his visit Wright stomped off to enjoy himself round London, which he was good at doing. After a short holiday in Dalmatia, he put the finishing touches to the text of the lectures back in Taliesin, unrepentant. They were promptly published that autumn in the handsome book that is here reprinted.
というわけで、 王立英国建築家協会でのスピーチにおいて、講演者が聴衆の心をつかむことはできなかった。イギリス訪問の最後にライトはロンドンを遊びまわったが、そういうことはお得意のようである。(クロマチアの)ダルマティアに寄った後、タリアセンに戻り、講演原稿に手を加えた---よくまあ懲りもせずに! その秋には立派な本として発行され、それがこのたび再販されたのである。
一体何なんだ、この皮肉たっぷりの序文の意図は?それに続いて、「くだらない」講演内容が、いかにも150年記念に相応しいハードカバーで 復刻されている意図は?じゃあ復刻しなければいいじゃないの、と言いたくなってくる。読んでいて腹立たしくなってしまった。
この腹立たしさは、ライトの研究者からよく受ける印象であるが。私は、彼らがライトを非難することに反対しているわけではない。非難するならなぜこういう企画に参加したり、あえて研究するのかと疑問に思うだけだ。ライトにたとえ非があったとしても、それを深堀したり貶したりすることに、研究者として何の意味があるのかが分からない。ライトの思想を素晴らしいと思う人をけん制しているのだろうか、だけど何のために?
帝国ホテルの末期にその建物の写真とエッセイを収めた、キャリー・ジェームス氏の本『Frank Lloyd Wright's Imperial Hotel』(1968)から引用して、この腹立たしさを収めよう。
Frank Lloyd Wright stood outside the mainstream of Western culture. It is the foreignness of his thought which is behind the strangeness of all his architecture. His idea of man and the world nearly opposite to ours; it is this we fail to grasp in our reaction to his art. To begin to understand Wright, it is necessary to put aside more of our traditional attitudes than may easily be done. It is necessary to see that his views of man and art were animated by the idea of unity, a sense of the singleness of all being and all life. This singleness, this inter-relatedness shaped his mind and his architecture in unusual and to us often incomprehensible ways. It is unity which ordered the being of the Imperial Hotel.
フランク・ロイド・ライトは西洋文化の主流ではなかった。彼の思想の不可思議さが、彼のすべての建築に一風変わった作風を与えている。人間と世界に対する彼の考えは、我々とはほぼ正反対のものであり、我々が彼の作品を完全に理解できないのはそのためである。ライトを理解するには、思い切って既成概念を外すことから始める必要がある。彼の頭の中には、人とアートが一体感を持って生き生きとしている、あらゆる存在と生命が一体となって息づいているという感覚がある。この一体感、この相互の密接な関係性が、彼の思想と建築を並外れた、そして我々にとって不可解な形にしているのだ。帝国ホテルをつかさどっているのは、この一体感なのである。
と言って、ジェームス氏は、分析的思考で作られる従来の建築は固定の物質として存在するのであり、この物質と精神を分けて考える我々の思考の二重構造を指摘する。ライトの有機建築は、時間と場所と人間の命と一体であるがゆえに、二重構造思考では理解が難しい。そしてその二重構造が、人間から生き生きした暮らしを奪い、物質的・経済的至上主義的な世界に放り込んだのだと。
Unity deals with change and dynamism.
一体感の中には、変化と動的な流れがある。
私はこれを読んで、仏教の無常と因果を思う。あるいは、福岡伸一さんのいう「動的平衡」を。すべては流動している、この一瞬も宇宙も膨張し、生命は進化と淘汰を続け、私の細胞は分割し続け排出し続ける。あらゆる存在は相関関係の中に起きる、つまり因果よって一時的に生じている現象に過ぎない。
あるいはインドの元始哲学ーーすべては見るものと見られるものという相対から始まったという、本来は何もないのに、無であるのに、相対的な見方がこの世を作ったという二元論。
ところが従来の建築は、永続する固定的なものとしてとらえられる。さらに土地の選定、坪単価、強度計算、耐震構造、建材、工賃、流行――あらゆる側面が個別分析的に集積されて経済的に処理される。生命体として、またそこに暮らす人たちと一体感のあるものとしてとらえられることはない。
こういう既成概念がある限り、ライトを虚心坦懐に理解しようとは思えないし、そうなると彼の言葉がいちいち皮肉に聞こえるのかもしれない。彼の根本思想が分からない人にはたしかに彼の言葉は分かりにくい。彼の文章は、たとえ英語のネイティブでも難解に思えるだろう。しかし、理解している人には、ネイティブじゃなくてもよくわかるのである。
現実的に考えると、当時も今も、建築のプロには受け入れがたい思想なのだろう。そういう意味でライトは単なる理想家として見られているが、それでも根強い人気がある。彼の鮮烈なメッセージが色褪せないのは、真実だからだと思いたい。
 |
| 1968年帝国ホテル解体直前の写真集 |