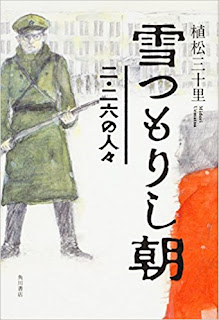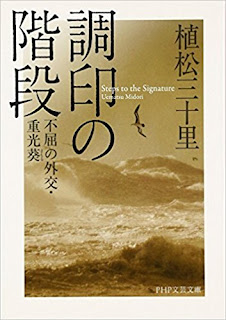この頃別のことにハマってしまって、あまりに更新していないので、非公開ブログから転記。
****************************************
2015年4月6日月曜日
4月になったら、4月になったら、と呪文のように唱えながら、何とか乗り越えてきた3月が、終わった途端のダウン。4月に入ってこそ何もできないでいる。洗濯も料理も掃除も何も。
昨日は甥の引っ越しの手伝いすら行けず、ダラダラと寝ていた。というか、それしかできない。少しでも動くとずっとだるくなってしまう。とくに足に痛みが走る。リンパを通って悪い菌が入ったかのように、足全体が痛くてかなわない。マッサージしてもお風呂に入っても痛い。
その痛みから気をそらすように、ダラダラと読書を続ける。あんまりダラダラ読んでいるので、なにを読んでいるかもわからない。先日俳句の知人が『井上ひさし全芝居その三』という分厚い本を送って来たので、それを適当に読んでいる。
吉本隆明の宮沢賢治論も面白かったが、井上ひさしの宮沢賢治の芝居もおもしろい。これから自分で宮沢賢治を読む際に、2人の論考がきっと参考になる事だろうとおもう。両者とも自分で調べて調べて、そして自分の中の歴史観とか人生論とか宗教観とか、そういうものをベースに宮沢賢治を論じている。
井上ひさしの芝居は、宮沢賢治の作品を芝居化しているのではなくて、彼の解釈した宮沢賢治の人生を芝居化しているのである。よって、だらだらと私は夏目漱石と芭蕉の芝居も読んでみて、彼の解釈している漱石と芭蕉にも触れた。吉本隆明も漱石についてはいろいろ言っているので、また比較してみようとおもう。
こうした知の巨人たちの作品とはまったく違ったテイストのものも読んだ。前から読みたくて、なかなか読む機会のなかった長編小説だ。野口晴哉ではないが、これもまた『風邪の効用』(笑)。村上春樹の『海辺のカフカ』
この小説の主人公である15歳の少年は、私にとってある意味、いちばんうらやましい存在だ。大人でも子供でもない年。汚れていないその心に、可能な限りの知識が詰まっている。私なんかが一生かかっても読めないほどの、高度な本をすでに読みつくしている少年。そんな生き方を可能にした内向的な生い立ちも気の毒だが、こういう少年が出てくるのはよくあるパターンで、村上春樹の小説には最も多いものの、よしもとばななとか、太宰治の幼少期なんかもそうなのかもしれない。
とにかく、早熟な少年。世の中を知らないくせして、知識だけはある。それも高等な。クラシック音楽にも現代音楽にも詳しい。背伸びしているのではなくて、その生い立ちや父の蔵書などから必然的に詳しくなっている。
同年代の子どもとは一線を画している。全然子供っぽくない、なぜなら、甘えさせてくれる親がいなかったから。現実を受け止め、澄んだ目で世の中を知った気になっているから、どこか醒めて斜めに世の中を見ている。かわいげがない。生意気である。でもそれに対する恥じらいもある。
こんな主人公の少年が、自分探しの旅に出かける。といってもそんなのんきなものではなくて、父のそばにいたら、父を殺してしまいそうな気がするのだろう、切羽詰った旅でもある。学校で学ぶものは何もなくなったのだ。というか、書物に書いてあることなら、すでに十分学んでいるし、それ以上のことは自分で学ぶ力があるから。
こういう一風変わった少年は、一風変わった大人に出会う。普通の人にはあまり縁のないタイプの。村上春樹やよしもとばななの頭の中にしか存在しないような、知的で素敵で中性的で傷をたくさん負いながら、それがすべて魅力になっているような、外見的にも美しい人々。だいたいがゲイでもある。トランスジェンダーやトランスジェネレーションを体現している人びと。国籍、時代、時空すらトランス出来そうな人びとだ。
そして少年はその一風変わった大人たちに助けられながら、自分を探していく・・・一言でいえば、村上春樹やよしもとばななのパターン化された小説である。設定はいつも世の中の社会経済活動とは切り離された、自然豊かな海辺、と舞台もきまっている。
徹頭徹尾現実離れした小説。登場人物は決して怒って声を荒げたり、俗っぽい愚痴をこぼしたりせず、モーツアルトとかスタインベックとかサルトルとか、なんでもいいのだけど、私にはよくわからない高度な会話を、なにかのメタファーとして話し合っている。結論はあるようなないような会話を。
しかし『海辺のカフカ』にはもう一人の主人公がいて、それもまた世間離れしている人なのだけど、そちらは文字も読めない知的障害のある老人である。猫と話ができる(村上流!)。そしてその老人に出会うトラックの運転手は、15歳の少年とは対極にあるような、俗っぽい青年だ。
15歳の少年のみずみずしい、そしてかなり屈折している恋愛(50歳ぐらいの女性との)の物語のとなりで、知的障害を持つ老人とトラック青年の不思議な旅物語が、シンクロしながら進んでいく。老人が知的障害を負うきっかけとなった戦中の謎の事件や、少年の父と思わしき男の奇怪な殺人事件が、シュールに絡み合いながら話は進む。
こんな変な複雑な話を、時空も、場所も、登場人物も、あちこち行ったり来たりさせながら、読者に読ませ続けるという作家の力には本当に恐れ入る。読み終わって、なにかを得たとかそういうことでもない。不思議な夢を見たというか。とくにこの小説の登場人物はものすごく多くて時間的にも複雑で、よくこんなものが書けたなと感心してしまう。世界中の言語に訳されて、とても評判がいいらしい。
ある書評によると、西洋的なテーマ(オディプスの呪い?とか)が描かれているのだそうだ。シュールなストーリーに、モンブランの万年筆とか銀の細いネックレスとか、シックなディテールがリアルで、自然描写も精緻を極めているし、やっぱり村上春樹ってすごいなと思う。
この作品は、蛭川幸雄が芝居にしたそうである。ロングランらしい。小説でもこんなに長くて複雑なのに、これを芝居にするのもすごいな。世の中にはすごい人がいっぱいいる。
吉本隆明、井上ひさし、村上春樹、蛭川幸雄・・・頭の中はいったいどうなっているのかなあ。
私の希望は、体調を治して、家じゅうをピカピカにすることぐらいしかないわ・・・